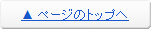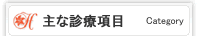一般歯科/小児歯科/口腔外科/矯正歯科/審美歯科/ホワイトニング/インプラント/訪問歯科/福岡の歯医者・有友会グループ
南区:中村司・比路江歯科医院/東区:ひろえ歯科医院/東区和白が丘:新宮歯科医院/博多区:吉塚ステーション歯科
福岡 東 博多 南 ゆめタウン博多 新宮 吉塚 ホワイトニング 小児 歯医者
福岡,東,南,博多
福岡,歯科,東,博多,南,歯医者,ゆめタウン博多,新宮,吉塚,ホワイトニング,小児歯科
口腔外科(こうくうげか)とは
口の中をのぞいて見えるすべての組織に生じた病気を診断して、治療をする診療科のことを口腔外科といいます。
痛みの部位や程度は個人差がありますが、左右どちらかだけに症状があらわれる場合が多いようです。
スプリント療法とは口の中に個別に製作したマウスピースをはめて、噛み合わせの高さを変えて関節の負荷を軽減する方法です。
薬物療法では、鎮痛消炎剤や筋弛緩剤等を服用して消炎を図ります。
親知らずは生えてくる場合と生えてこない場合(又は最初から無い場合)があるのですが、この歯は抜歯してしまった方が良い場合もあります。
ただし、親知らずは絶対に抜かなくてはいけないという訳ではなく、残しておいた方が良い場合もあります。
ただ、親知らずは正しい位置に生えてくることがあまりなく、横にはえたり、生えきらなかったりすることがほとんどで、周りの歯茎が腫れたり、隣の歯までむし歯になることが多く、トラブルの原因になりがちです。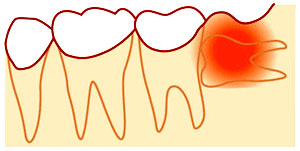
【診断、治療箇所】
歯・歯茎・舌・頬の粘膜・舌の付け根・上アゴ・下アゴ・唇・唾液腺顔やアゴの形をつくっている骨・アゴの関節など
こんな時は口腔外科にご相談を
- 親知らずが痛い、もしくは抜きたい
- アゴがカクカクなる
- 口内炎が治らない
- アゴや顔が変形している
- 舌がヒリヒリする
顎関節症とは
顎関節症とは、顎の関節とその周辺に障害が起きる病気で、顎を動かしにくくなって口を大きく開けることができなくなる、口を開け閉めする時にカクンとか、シャリシャリと音がする、口を開けると顎や耳の穴のすぐ脇にある関節が痛む、食べ物がよく噛めなくなる、顎の周辺やこめかみなどが痛む、首や肩がこる、などの症状があらわれます。痛みの部位や程度は個人差がありますが、左右どちらかだけに症状があらわれる場合が多いようです。
また、顎とその周辺だけでなく、頭痛、めまい、耳鳴り、手足のしびれなどの症状を訴える人もいます。
顎関節症はここ10数年で急増しており、20~30代の女性に多く見られます。
なぜ男性より女性の方が多いのかはまだよくわかっておらず、「女性の方が男性より骨格や筋肉が弱いから」あるいは、「女性ホルモンが関係する」など、いろいろな説があります。
こんな方は顎関節症に要注意!
- 左右どちらか一方だけで噛む癖がある方
- 噛み合わせが悪い方
- 歯ぎしり・頬杖をつく癖がある方
- ストレスなどで歯を食いしばる癖がある方
顎関節症の治療
治療の主流は静的治療と呼ばれるスプリント療法・薬物療法等で、動的療法と呼ばれる外科手術はあまり選択されません。スプリント療法とは口の中に個別に製作したマウスピースをはめて、噛み合わせの高さを変えて関節の負荷を軽減する方法です。
薬物療法では、鎮痛消炎剤や筋弛緩剤等を服用して消炎を図ります。
親知らずとは
「親知らず(親不知・おやしらず)」とは、前から数えて8番目の歯である「第三大臼歯」のことです。親知らずは生えてくる場合と生えてこない場合(又は最初から無い場合)があるのですが、この歯は抜歯してしまった方が良い場合もあります。
ただし、親知らずは絶対に抜かなくてはいけないという訳ではなく、残しておいた方が良い場合もあります。

親知らず(親不知・おやしらず)を抜く理由
もちろん普通に生えていて、普通に噛んでいる親知らずは無理に抜く必要はありません。ただ、親知らずは正しい位置に生えてくることがあまりなく、横にはえたり、生えきらなかったりすることがほとんどで、周りの歯茎が腫れたり、隣の歯までむし歯になることが多く、トラブルの原因になりがちです。
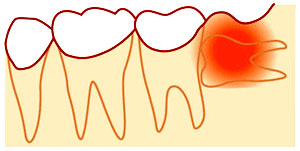
親知らずの生え方によっては歯磨きをきちんとすることが不可能な場合があり、そのような場合には将来的に虫歯や歯周病になってしまう可能性が非常に高くなります。
しかも、その場合には大事な手前の歯(第二大臼歯)も巻き込んでしまうので、そうなる前に抜いてしまうという訳です。
行ったその日に抜いてもらえるの?
難しい抜歯の場合は、術前の診査、診断が重要になります。基本的には、初診の日は診査、診断に当て、その次の回の予約をしていただき、抜歯を行います。初診の段階で腫れているようなら、薬で腫れを抑えてから 抜歯します。
| 抜歯治療の流れ |
|---|
| 初診日 診査診断 抜歯の予約 |
| ↓ |
| 抜歯当日 |
| ↓ |
| 抜歯の次の日に傷口の消毒 |
| ↓ |
| 抜歯日に縫合していれば抜糸 |
| ↓ |
| 治癒を待って終了 |
福岡,歯科,東,博多,南,ゆめタウン博多,新宮,吉塚,ホワイトニング,小児,歯医者

南区の歯医者さん
福岡,東,博多,南,ゆめタウン博多,新宮,吉塚,ホワイトニング,小児,歯医者
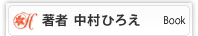 |
|---|
 |
福岡,博多,南,ゆめタウン博多,新宮,吉塚,ホワイトニング,小児,歯医者